第33号:高付加価値事業の成否を決める巻き込み力
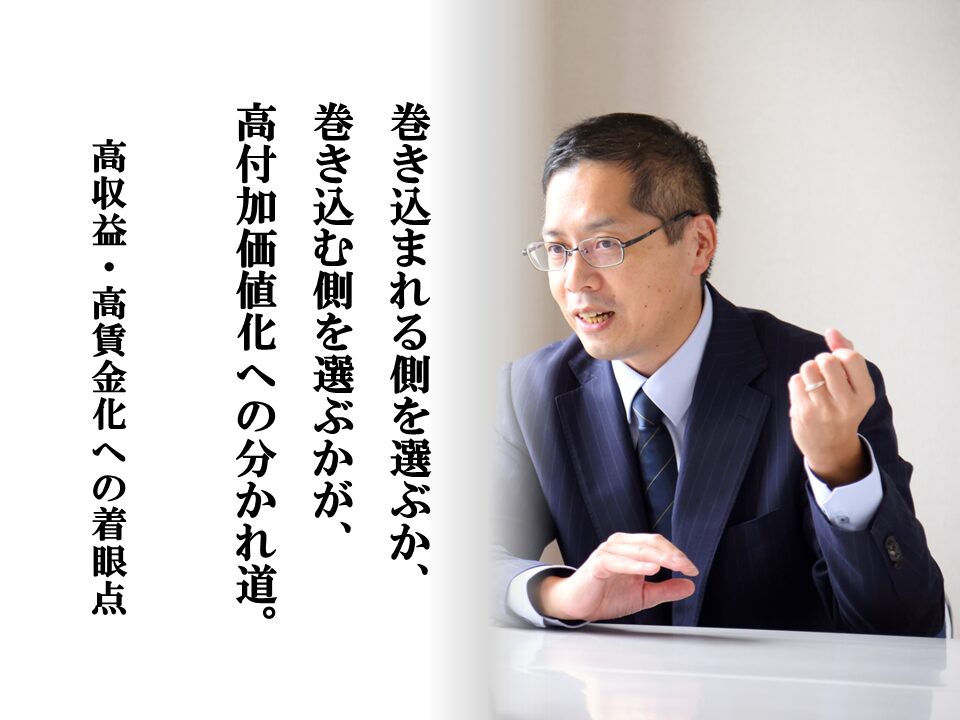
「シライ先生、これからは我が社から積極的に技術の普及を目指すわけですが、待ちの姿勢で仕事を受けてきた我が社にとって、何を発信すればいいのかがイメージできていません」
部品加工会社を営むA社長のご発言です。これまで特定企業の下請け事業者として経営してきましたが、産業構造の変化に対応していくべく、自らの加工技術力をウリにして、良い単価で新たな取引先を開拓していく目標を掲げています。
加工、設計、建築、検査などの受注型事業の場合、その産業構造上、待ちの姿勢になりやすい特徴があります。もちろん、営業を雇用して顧客開拓している会社もあるでしょう。
しかし中小規模の場合、営業といってもメイン業務は納品ついでのルートセールスだったりすることも多く、既存取引先のフォロー程度のことはできても、大きく受注量や受注単価を増やしていく活動に直接結びついていなかったりします。
営業先において業界の動向や受注見込みについての話はするにしても、特段それ以上の話が出ず、基本的には「受注見込みの確認と注文取り」のような営業になってしまっていることも珍しくありません。もちろん、それはそれとして重要な業務ではありますが、こと高付加価値事業への転換を目指すのであれば、この活動の延長にそれを実現するとはイメージしにくいでしょう。
高付加価値事業とは、第一にお客様の大きな願望にフォーカスした、高い価値を持つサービス・技術・ノウハウ・モノを提供することで実現します。
会社の強みを価値に転換し、その価値を落とすことなく売っていく仕組み作り、すなわち高付加価値事業構造を設計することこそ、まずやらなければならないことです。その構築の仕方はコンサルティングでご支援していくことになるわけですが、テクニック的なことよりも重要なことがあります。それはビジネスを動かす「軸」の考え方です。
A社は発注元の会社が要求したものを作ることで収益を得ています。A社が要求した通りのものを要求レベルで作れるということは業務としては重要です。しかし事業としてみた場合、この取引の「軸」、つまり主たる価値創造者は誰かと言えば、発注元になります。
もちろん、A社の技術力に価値がないと言っているわけではありません。しかし現実を見れば、A社にしかできない加工ではないこともまた事実であり、発注元が価値を設計したことに対する具現化の部分の価値は相対的に低くなります。
つまり、軸は取引先にあり、A社はその軸の周りを取り巻いている側になっている、ということです。
A社の技術力には価値があります。しかしただ相手が要求していることに応えるだけでは、その仕事の価値の総和も、相対的なA社の価値も大きくなりません。
A社が高い価値をつけ、これを価格に変えていくには、「相手のより大きな願望成就に応えられる独自のサービスを提案できるカタチ」にすることで、"相手を巻き込める軸"を確立する必要があります。
表現を変えれば、「御社が本当に望んでいることは、これこれじゃないですか?当社では、こういうカタチでその望みを叶えることが出来ますよ。これがあったら、御社の競争力も更に強くなりませんか?」という提案を出来る状態が、軸がある状態です。そしてこの軸の中に、お客様を巻き込んでいくのです。
もちろん、お客様の要望を聞かずに自社の軸を押し付けろと言っているのではありません。ビジネスは喧嘩ではなく協力です。
しかし協力にも「ただ要求されたことをやり続ける協力」と「互いに軸を持ち寄ってより大きな価値を生み出す協力」という二通りがあることに留意が必要です。高い付加価値を生み出す事業とは、自らの軸を持って、これを発信・提案していくことで、お客様に大きな価値を提供するという後者のあり方を目指す必要があるのです。
たしかにビジネスはお客様に奉仕して初めて成り立ちますから、お客様の願望を叶えるように自社が動くことになります。
しかし、その叶え方であったり、顧客すら見落としていた何かへの貢献、といったプラスアルファの部分に対して、自社の強い拘りと独自性がないのであれば、あなたの会社に仕事を依頼しなければならない理由がありません。他の会社でもほぼ同じようなことをやってくれるのであれば、価格で比較される結果になることは自明の理です。
これが「御社のご要望にお応えして参ります」という御用聞き型の危険なところなのです。「ご要望にお応えして~」というのは確かに聞き触りが良いですし、言われた側からすれば「ここは自分の要求する通りにやってくれるのだろう」という安心感があります。
しかし「ご要望にお応えして~」というのは、実に手っ取り早い、ノーリスクで安上がりな、誰でも発することが出来るメッセージでもある、という側面にも着目する必要があります。極端に言えば、このメッセージは何かを言っているようで何も言っていないのです。そこに、お客様を巻き込んでいくような拘りや軸はありません。
重要なことは、顧客の強い願望を見つけ出し、独自の視点からの独自の問題解決法を持ち、これを提案できるカタチにすることです。
なぜなら、人は提案されることではじめて、自分でも気が付かない真の願望に気が付くことが出来るからです。「言われてみれば、たしかにそれ、いいかも・・」という認知変容をお客様の中に起こすことで、お客様自身想定していないようなプラスのメリットを享受でき、それに対する対価を支払うことに繋がるのです。
自社の軸を形成して、軸を中心にお客様を巻き込むという行為を別の表現をすれば「この指止まれ」です。「私たちはこの思想と方法論によって、御社の競争力が更に高まると信じています。利用してみませんか?」という積極的態度が重要です。たとえ業界における下請けという位置付けだとしても、確固たる軸を持つことで大きな収益に繋げることは可能なのです。
そしてこの巻き込み力というものは、社員に対しても効果的に発揮できる力になります。確固たる事業軸を確立し、巻き込み力を発揮することで、社員に対する見方が「業務を遂行する者」という発想から「社長の描く未来構想を実現していく協力者」という発想に変わるのです。これにより、社員が思うような動きをしないという事象に対しても見方が変わります。
前者のように見る社長は、何か組織で上手くいかないことがあると「社員に問題がある」と考えます。後者のように見る社長は「自分の巻き込み力の問題」と捉えます。
重要なことは、事業の軸を明確にしたうえで、社長の巻き込み力を上げていく「仕組み」を構築することです。社長のパーソナリティや事業内容に関わらず、お客様を巻き込み、社員を巻き込んでいく仕組みを実装するのです。
社長自身のパーソナリティや内に秘めている考え方、そして独自性にこそ、高付加価値事業作りの種子です。これが顧客の大きな願望を叶え、利益を生み出し、社長と社員の報酬を大きくしていく源泉です。その社長の力を、最大限の影響力を持つカタチに変換していく仕組み作りに力点を置くべきです。
あなたは、事業の確固たる軸を作り、これを巻き込み力に変えていき、関わる人々(お客様や社員)に影響を与え続ける仕組みを手に入れていますか?
コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。

