数字で語れる社長 vs 数字で語れない社長
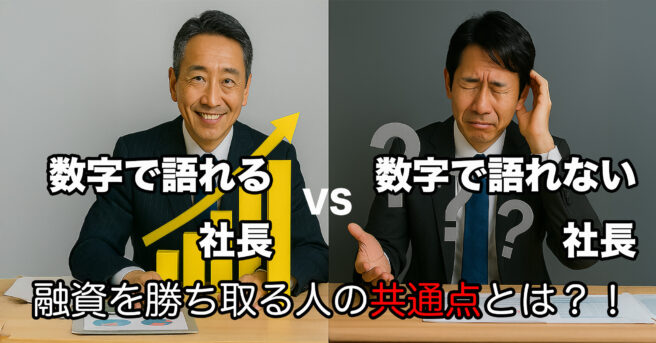
「いや〜、資金繰りには自信があったんですが、銀行との面談で『その数字の根拠は?』と聞かれて、言葉に詰まってしまって……」
これは、当社のセミナーに参加された製造業の社長の声です。過去の実績に自信があったとしても、いざ銀行との面談となると、数字で語ることの難しさに直面する経営者は少なくありません。
「決算書は税理士に任せている」「感覚的にはうまくいっている」―そうした姿勢が、銀行との信頼構築の障壁になっていることに気づかない経営者も多く見受けられます。
もちろん、会計の専門家である必要はありません。しかし、融資を受けたいならば、最低限の財務理解と、それを自分の言葉で説明する力が求められます。
銀行は、数字そのものよりも「その数字を理解し、未来をどう描こうとしているか」に注目しています。数字が読めていない、語れないということは、「返済の見通しが立っていない」「経営の状況を自分で把握できていない」と見なされる原因になるのです。
つまり、数字に強いかどうかが、銀行との信頼を築けるかどうかを左右する最重要ポイントなのです。
一方で、数字に強い社長は、財務三表をもとに自社の現状と将来像を明確に語ります。たとえ業績が下降気味でも、「なぜそうなっているのか」「どんな打ち手があるのか」を数字で説明できれば、銀行の見る目はまったく違ってきます。
この違いが、融資の結果を大きく分けるのです。
では、なぜここまで差がつくのか。そして、数字で語れる社長になるにはどうすればいいのか―それを本コラムでひも解いていきます。
はじめに
中小企業の経営において、銀行との関係は資金調達や成長のチャンスに直結します。にもかかわらず、面談の場で「売上は伸びています」「頑張って返します」といった抽象的な言葉しか出てこない社長が少なくありません。結果として、「よく分からない」「信用しづらい」と判断され、希望した融資額が通らないケースが後を絶たないのです。
一方で、同じような業績の企業でも、社長が自ら数字を理解し、説明できる会社は、銀行からの評価もまったく違います。そこに業種や地域、企業規模は関係ありません。数字をどう扱っているかが、信頼を得る大きな判断基準になっているのです。
では、数字で語れる社長とは、どんな準備をし、どのように銀行と向き合っているのでしょうか?そして、数字で語れない社長は、なぜ損をしてしまうのか?
実は、融資を勝ち取るために必要なのは、難解な会計知識でも、完璧な経営計画書でもありません。
銀行の担当者が本当に見ているのは、社長自身の数字に対する感度と姿勢です。言い換えれば、「数字を味方につけられる社長」こそが、信頼され、チャンスをつかむことができるのです。
本コラムでは、数字で語れる社長と語れない社長の違いを明らかにし、銀行に選ばれる経営者になるために何をすべきかを実例とともにお伝えします。数字に苦手意識がある方こそ、ぜひ最後までご覧ください。
1. 銀行が社長を見るポイントは「数字に強いかどうか」
銀行から融資を受ける際、多くの社長が「うちは黒字だし、売上も伸びている。これなら通るはずだ」と思い込んでしまいます。確かに、財務内容は重要です。しかし、実際にはそれだけでは不十分です。
銀行が本当に見ているのは、「この社長にお金を預けて、本当に大丈夫か?」という視点です。ここで問われるのが、経営者としての“数字力”です。どんなに売上や利益が出ていても、社長自身が数字を理解していなければ、銀行は「この人に任せるのは不安だ」と判断します。
銀行は、業績そのものよりも「その数字をどう読み、どう未来につなげているか」を見ています。数字で語れる社長と語れない社長の差は、融資の結果に大きな違いを生むのです。
1.1 銀行は「社長の数字力」で融資可否を判断する
「過去の数字」よりも「未来の展望」。これが銀行の融資判断の基本です。売上や利益がどれだけ出ていても、それが今後も維持・成長できるのかは、社長の考え方と判断力にかかっています。
そこで問われるのが、数字をどう捉え、どう説明できるかという力です。
たとえば、銀行の担当者に「この売上増加の理由は?」「今期の資金繰り計画は?」と聞かれたときに、根拠ある数字とロジックで即答できる社長は、確実に評価されます。
一方で、「感覚的にいけると思います」「たぶん売上は伸びると思います」といった曖昧な発言しかできない社長に対しては、どれだけ数字が良くても疑念を持たれてしまいます。
数字で語れない社長は、それだけで“返済の見通しが立たない人”と見なされるリスクがあります。
数字力とは、決算書を完璧に読めることではありません。自社の数字をどう解釈し、どう説明できるかが評価の対象なのです。
1.2 財務三表の読み書きができる社長は信頼される
財務三表とは、「損益計算書(PL)」「貸借対照表(BS)」「キャッシュフロー計算書(CF)」の3つです。これらを「読める」だけではなく、「語れる」経営者が、銀行から強く信頼されます。
たとえば、PL(損益計算書)を見て「今期は粗利率が●%改善して営業利益が回復した」と説明できるか。BS(貸借対照表)で「借入金の割合が減り、自己資本比率が向上している」と語れるか。CF(キャッシュフロー計算書)で「今期は営業キャッシュがプラスで安定している」と説明できるか。
このように財務三表を使って自社の状況を説明できる社長は、「経営を数字で考えている人」として高く評価されます。
また、銀行との面談時に「この部分は税理士に聞かないと分かりません」と答えてしまう社長は、評価を大きく下げてしまいます。なぜなら、銀行は「この会社は誰が経営をしているのか?」と不安に感じてしまうからです。
財務三表は、会社の健康診断書です。最低限の読み方・語り方ができなければ、信頼を得ることはできません。
難しく考える必要はありません。まずは自社のPLとBSを見ながら、「なぜこうなっているのか」を一つずつ確認することから始めましょう。それだけでも、銀行からの見え方は確実に変わってきます。
1.3 数字で語れない社長が銀行に与える“3つの不安”
数字に強いかどうかは、銀行との関係性を左右します。逆に言えば、数字で語れない社長は、知らないうちに銀行から“不安”を抱かれているのです。その代表的な3つをご紹介します。
(1)「返済できるのか?」という不安
銀行は融資先に対し、返済の確実性を最も重視します。
そのため、「いくら借りたいか」よりも「どうやって返すのか」が明確になっていなければ、融資は通りません。
「頑張って返します」「売上が上がる予定なので大丈夫です」といった抽象的な返答では、銀行は納得しません。具体的なキャッシュフロー計画、利益の見通し、回収シナリオなどを数字で語ることが求められます。
数字で返済の道筋を説明できない社長には、安心してお金を預けることはできません。
(2)「経営判断ができるのか?」という不安
数字に向き合わない社長は、往々にして「感覚で判断している」傾向があります。値引きをする、在庫を増やす、採用を強化するといった意思決定が、数字の裏付けなしに行われると、経営の舵取りが不安定になります。
銀行は、「この社長は意思決定の精度が高いか?」を見ています。そして、その判断はほぼすべて「数字に基づいているかどうか」で決まります。
数字を使って経営判断ができる社長は、変化の多い時代でも冷静に舵を切れる人として評価されます。
(3)「対話ができるのか?」という不安
意外に見落とされがちなのが、「コミュニケーション」の観点です。銀行との関係は、一度融資を受けて終わりではありません。返済状況の報告、次の資金計画、状況変化への対応など、継続的な“対話”が求められます。
その対話のベースになるのが、やはり「数字」です。
「営業利益は前年よりも○○円減ったが、広告費が一時的に増加したためで、来期は回復見込みです」といった数字を交えた説明ができるかどうかが、信頼を左右します。
数字で意思疎通ができない社長は、銀行から“本音を伝えにくい相手”と見られてしまいます。
このように、数字で語れないことがもたらす不信感は、1つひとつは小さくても、結果として大きなマイナス評価につながります。
しかし逆に言えば、数字に強くなることで、こうした不安をすべて払拭することができるのです。
融資を受けるかどうかに関係なく、経営者である以上、数字で語れる力は“当たり前”の素養になりつつあります。
次章では、数字で語れる社長たちが、日頃どのような“準備”をしているのかを詳しく見ていきましょう。
2. 数字で語れる社長がやっている“準備”とは?
数字に強い社長は、融資の申込みにあたって、他の経営者が見落としがちな「ある準備」を怠りません。
それは、融資の申請書類を整えることでも、立派な事業計画書を作ることでもありません。
銀行が求める“判断材料”を先回りして用意する――それが、数字で語れる社長が共通してやっている準備です。
そして、その準備は決して難しいことではなく、今日からでも始められることばかりです。ここでは、特に効果の高い3つの準備について解説します。
2.1 融資前に必ず作る「資金繰り表」とは
銀行がまず確認するのは、「この会社は借りたお金を返せるのか?」という点です。
いくら夢のある事業でも、返済計画が曖昧では融資は通りません。そこで必要になるのが、「資金繰り表」です。
資金繰り表とは、売上や入金、仕入や返済、固定費などの支出を月単位で記載し、今後の資金残高を予測する一覧表です。これを見ることで、会社がいつ、いくら資金を使い、どれだけ残るのかが一目でわかります。
銀行は、事業の可能性よりもまず、資金の流れに目を向けます。つまり、「現実的に返済ができるかどうか」を確認しているのです。
資金繰り表の中身は難しくありません。たとえば、以下のような項目があれば十分です。
・月別の売上予測
・入金タイミング(請求→回収のズレ)
・仕入・外注費の支払い予定
・人件費や家賃、税金などの固定支出
・借入金の返済額とタイミング
そして、何よりも重要なのが、この資金繰り表を「社長自身が理解し、自分の言葉で説明できる状態」にしておくことです。
「経理に作らせました」「内容は見ていません」では、せっかくの資料も意味を持ちません。たとえ完璧でなくても、自分の頭で理解し、伝えられることが、数字で語れる社長への第一歩なのです。
2.2 損益だけでなく「利益率」で語る
銀行に対して、「今期の売上は1億円です」と伝えても、それだけでは意味がありません。なぜなら、売上がいくらあっても、利益が出ていなければ、返済には回せないからです。
だからこそ、数字で語れる社長は売上額よりも「利益率」で経営を語るのです。
たとえば、
・「粗利率を3%改善したので、同じ売上でも利益が出るようになった」
・「販管費率を抑えるために、広告戦略を見直した」
・「高粗利の商品比率を上げたことで営業利益が安定している」
このように利益構造の“中身”を分析して語れる経営者は、銀行からの評価が非常に高くなります。
一方で、「とにかく売上を伸ばします」「社員に頑張ってもらいます」といった精神論に終始する社長には、返済の現実味が感じられず、不安を与えるだけです。
また、「前年と比べてどう変わったか」「どの部門が利益を出しているのか」「どこに改善の余地があるか」といったことを数値で見せることができれば、“経営の見通しが立っている社長”として銀行に安心感を与えることができます。
売上は「結果」に過ぎません。利益率は「構造」です。構造を理解している社長こそ、経営をコントロールできる人なのです。
2.3 「なぜこの融資が必要か」を数字で説明するシナリオを準備
最後に、銀行面談でもっとも重要な質問が、「今回の融資は何に使いますか?」というものです。
ここで明確に答えられないと、たとえ資金繰りが苦しいとしても、融資は通りません。
数字で語れる社長は、この質問に対し、“目的”と“返済見込み”をセットで数字で説明する準備をしています。
たとえば、
・「今回の設備投資500万円は、新商品の量産体制構築のため。完成後は月間出荷数が3倍になり、月商が100万円増える見込み」
・「人員補強費用200万円で営業1名を採用。月平均の成約率から逆算すると、3ヶ月後には投資分を回収できる想定」
・「今後1年間の資金繰りシミュレーションでは、借入金を含めても毎月キャッシュは黒字で推移する計画」
このように、「借りたお金がどう活きて、どう回収され、どう返済されるか」まで語れる社長が、銀行に選ばれるのです。
反対に、「資金繰りが厳しいので…」「とりあえず借りられるなら借りたいです」といった説明では、「計画性がない」と見なされ、否決されることが珍しくありません。
シナリオとは、想像ではなく、数字と根拠に基づいた“説明書”です。決して格好いい資料でなくてもいいのです。重要なのは、自分の頭で考え、数字で話せる状態を整えておくことです。
数字で語れる社長は、特別な会計知識があるわけではありません。ただ、銀行が不安に思うポイントを事前に想定し、必要な数字を準備し、自分の言葉で説明するだけです。
そして、それは今日からでも始められます。
資金繰り表を作ってみる、粗利率を確認してみる、次の投資の回収見込みをシミュレーションしてみる―その一つひとつの積み重ねが、銀行との信頼をつくっていくのです。
数字で語れる社長になる準備は、すでにあなたの手の中にあります。
次章では、数字で語れない社長がなぜ損をするのか、その背景にある“誤解”を解き明かしていきます。
3. 数字で語れない社長が陥る3つの誤解
銀行との融資交渉で成果を上げられない社長には、ある共通点があります。それは、「数字で語れない」ということ。
しかし、これは単なるスキル不足というよりも、“思い込み”に支配されたまま、誤った方向に努力してしまっていることが原因です。
本章では、数字で語れない社長が無意識に陥っている3つの代表的な誤解と、それによって何が失われているのかを明らかにします。自社にも当てはまる項目がないか、ぜひ確認しながら読み進めてください。
3.1 「税理士が見てるから大丈夫」は危険な思い込み
「決算書は税理士に任せてあるので、自分はノータッチでいい」
―このように考えている社長は意外と多くいます。確かに、帳簿や申告の専門的な処理は税理士に任せるのが合理的です。
しかし、銀行との面談で問われているのは、“税理士の理解力”ではなく、“社長の理解力”です。
銀行は「この人は自分の会社の数字をきちんと把握しているのか」「経営の責任を自覚しているのか」を見ています。
「その件は税理士に聞いてください」と返された瞬間、信頼度はガクッと下がります。
なぜなら、銀行にとっての“取引相手”は、あくまで社長本人だからです。
また、税理士は過去の数字を整理する役割が中心であり、未来の計画や資金調達に関しては、必ずしも積極的に関与してくれるとは限りません。
経営判断を下すのは、最終的に社長自身なのです。
数字を理解することは、任せる・任せない以前に、経営者としての最低限の責任です。
どれだけ優秀な税理士がいても、社長が自ら数字を語れなければ、銀行からの信頼は得られません。
3.2 「数字に弱いのは性格だから仕方ない」は経営者失格?
「私は文系だから」「昔から数学が苦手だったので…」
―こうした理由から、数字と向き合うことを避け続けている社長も少なくありません。数字に対する苦手意識は誰にでもあるものですし、それ自体は悪いことではありません。
問題なのは、“苦手だから見ないままにしている”という姿勢こそが、経営者として最も危うい状態だということです。
経営における数字とは、ただのデータや表計算ではありません。利益率や固定費、借入残高、回収サイトといった数値は、すべて「意思決定の材料」です。これらを避けてしまうと、経営の舵取りは“感覚頼り”になってしまいます。
さらに、現代は会計ツールや経営ダッシュボードなど、数字を簡単に可視化する仕組みがいくらでも整っています。つまり、もはや「数字に弱いこと」を言い訳にできる時代ではないということです。
そして実は、多くの成功している経営者も、最初は数字が得意だったわけではありません。
「毎月試算表を見る」「資金繰り表をつける」「会議で数字を交えて話す」といった小さな習慣の積み重ねが、“数字を語る力”を育てているのです。
経営者に必要なのは、完璧な計算力ではなく、数字と向き合う姿勢です。
“苦手”を乗り越える覚悟があるかどうか、それが問われているのです。
3.3 「売上が上がってるから大丈夫」は幻想
売上の数字だけを見て、「今月は順調だ」「前年比プラスだから問題ない」と安心していませんか?
これは、非常に多くの社長が抱いている最大の落とし穴です。
売上が増えていても、利益が出ていないケースは少なくありません。むしろ、売上を追いかけるあまり、値引きや無理な受注で利益を圧迫している企業の方が多いほどです。
また、売上の入金タイミングと、仕入・外注・人件費などの支払いタイミングがズレていれば、一時的に資金ショートが起こる可能性もあります。
つまり、黒字でも倒産する「黒字倒産」は、どの企業にも起こり得る現実なのです。
銀行は、売上よりも「利益構造」と「キャッシュの流れ」を見ています。
どれだけ売れていても、「それが利益に結びついているか?」「資金繰りに無理がないか?」という視点で判断しているのです。
売上=安心、という思い込みは、経営判断を誤らせる最大の要因です。
例えば、次のような数字が見えているかどうかが、経営の質を分けます。
・売上総利益率(粗利率)はどう変化しているか?
・一番利益率の高い商品やサービスは何か?
・固定費を吸収するために、いくらの売上が必要か?
これらの視点を持てるかどうかが、数字で語れる経営者と、売上だけを追う経営者との分岐点になります。
本章で紹介した3つの誤解は、決して珍しいことではありません。
むしろ、現場で奮闘する中小企業の多くの経営者が、どれかに当てはまっていると言っても過言ではないでしょう。
ただし、誤解は「気づき」によって修正することができます。
そしてその先には、数字で語れる社長として、銀行や社員から信頼され、経営判断に自信を持てる世界が広がっています。
まずは、誤解を認め、正しく向き合うこと。それが、数字に強くなる最初の一歩です。
次章では、銀行が「この社長には貸したい」と思う経営者に共通する行動や視点についてご紹介します。
4. 融資を勝ち取る社長の“共通点”とは?
銀行との面談を受けるとき、「決算書は整っているし、業績も悪くないから大丈夫だろう」と思っていたのに、融資が希望額に届かなかった─こうしたケースは少なくありません。
実際には、同じような業績でも、銀行に「ぜひこの社長に貸したい」と思わせる人と、そうでない人が存在します。では、その違いはどこにあるのか?
本章では、実際に融資を勝ち取っている社長たちに共通する3つの要素を解説します。これは特別な能力ではなく、誰でも身につけられる“習慣”や“意識”の差です。
4.1 事業計画書を“数字で語れる”資料にしている
銀行に提出する事業計画書。表紙を立派に作ったり、文章を丁寧に書いたりすることに時間をかけている経営者は少なくありません。しかし、実際に銀行が見ているのはそこではありません。
銀行が見ているのは、数字の裏付けがあるかどうか、計画に現実味があるかどうかです。
例えば、
・売上計画に対して、商談数・成約率・単価などの論理的な積み上げがあるか
・人件費や原価、販売管理費の増減に対する根拠が明記されているか
・借入金の返済原資がどのように確保されるのか、資金繰りの見通しが説明されているか
こうした“数字に裏打ちされた計画書”を提出できる経営者は、融資の場面で非常に強い武器を持っていることになります。
反対に、「今後は売上を倍にします」「新しい市場を開拓して業績を上げます」といった抽象的な表現ばかりでは、いくら夢があっても、銀行は動きません。
銀行は、現実的に数字で説明できる事業計画にこそ、資金を託したいと感じるのです。
数字が入っているからといって、派手なグラフや難しい表は必要ありません。むしろ、簡単な表やシンプルな数値で、「社長自身が語れる計画」になっていることの方がはるかに重要です。
4.2 質問に即答できる「財務リテラシー」がある
面談の中で、銀行の担当者が「粗利率は何%ですか?」「昨年度の営業利益は?」「借入残高はどれくらいですか?」と聞いてくる場面はよくあります。
このとき、すぐに答えられる社長と、答えられない社長とでは、印象に大きな差が出ます。
財務リテラシーとは、“経理知識”ではなく、“自社の数字に対する理解度”です。
銀行は、決して専門家のような分析力を求めているわけではありません。大事なのは、「自分の会社の数字をどれくらい把握しているか」です。
例えば、
・「今月の粗利率は34.6%。前年同月よりも1.2ポイント改善しています」
・「手元資金は月商の1.5ヶ月分。資金繰りの計画も組んでいます」
・「昨年度の営業利益は800万円。今期は販管費を絞って1,000万円を目指しています」
こういった回答を自然にできる社長は、それだけで「この会社は社長がしっかり数字を見ている」と安心感を与えることができます。
一方、「あまり見てないので……」「たぶんそれくらいだったと思います」といった曖昧な回答が続けば、銀行側は「この人にお金を託しても大丈夫だろうか」と不安を感じてしまいます。
数字は“暗記”する必要はありません。ただし、最低限の財務指標を把握し、自分の言葉で語れるようにしておくことが、結果的に融資の通過率を大きく左右します。
4.3 数字で「未来を語る力」がある
過去の数字を把握しているだけでは、銀行の信頼は十分ではありません。さらに大切なのが、「未来を数字で語る力」です。
銀行は、これからお金を貸す相手が、どんな未来を描いているか、そしてそれがどれだけ実現可能かを見極めようとします。
たとえば、
・「今後3年間で営業利益を1,000万円から1,500万円に伸ばす計画。そのために固定費比率を年2%ずつ改善します」
・「新商品の売上構成比を3割にし、粗利率の引き上げを狙います」
・「人員1名追加によって、1人あたりの生産性を20%高め、売上は年1,000万円増加する見込みです」
このように、未来を数字で描く力がある社長は、銀行から見て「計画性があり、意思決定の根拠が明確な人」として高く評価されます。
夢や熱意だけでは伝わらない現実があるからこそ、数字が未来への“道しるべ”になるのです。
ここで重要なのは、実現可能性です。無理な売上計画や急激な成長目標は、かえってマイナス評価につながります。むしろ、数字をもとに着実な成長シナリオを描ける方が、銀行には好印象を与えます。
融資を勝ち取る社長に共通するのは、特別な才能でも人脈でもありません。
自社の数字を把握し、相手の立場に立って、誠実に語れる準備をしているだけなのです。
計画書に数字を入れる。財務指標を押さえる。未来の展望を数字で描いてみる――この一つひとつの積み重ねが、銀行との信頼関係を築き、融資を勝ち取る結果に直結していきます。
数字で未来を語れる社長にこそ、銀行は「応援したい」と感じるのです。
次章では、そうした“数字で語れる社長”になるために、明日から実践できる行動をご紹介していきます。
5. 今すぐ始める“数字で語れる社長”への第一歩
「数字に強くなりたい」「銀行と対等に話したい」「社員に経営の方向性を示したい」——こうした思いを持ちながらも、「何から始めればいいのかわからない」と感じている経営者は少なくありません。
大丈夫です。“数字で語れる社長”になることは、特別な才能ではなく、日々の習慣で誰でも身につけられるものです。
ここでは、初心者の方でもすぐに実践でき、成果につながる3つのステップをご紹介します。どれも、明日から取り組める内容です。
5.1. 「月次試算表」を毎月見るクセをつける
まず取り組んでいただきたいのが、「月次試算表」を毎月必ず確認することです。
月次試算表とは、月ごとの損益や資産状況をまとめた資料で、いわば会社の“健康診断結果”のようなものです。ところが多くの中小企業では、この資料が「税理士に任せきり」「年に一度しか見ない」という状態になっています。
しかし、経営者自身が毎月の数字を確認し、会社の状態を自分で把握することが、経営の第一歩です。
見るべきポイントは、次の3つだけでも十分です。
・今月の売上と昨年同月の比較(前年比)
・今月の粗利率と前年同月の粗利率
・経常利益が黒字か赤字か
この3点を「毎月、数字で確認する」ことを習慣にするだけで、会社の状態が驚くほどクリアに見えてきます。
また、数字を見ることに慣れてくると、「あれ?人件費が急に増えてる」「粗利が落ちてるのに売上は伸びてる。なぜだ?」といった気づきが生まれます。この“気づき”こそが、次の経営判断を正しく導く土台になります。
5.2. 売上より「利益構造」を把握する
数字を見る習慣が身についてきたら、次に注目すべきは「利益構造」です。
売上が増えれば会社が良くなる—そう思いがちですが、実際には売上が増えても、利益が出ていない会社はたくさんあります。
本当に見るべきは、「どの商品・サービスがどれくらいの利益を出しているのか」「利益率の高いものと低いもののバランス」です。
たとえば、
・商品Aの売上は月500万円だが、利益率が10%(利益は50万円)
・商品Bの売上は月200万円だが、利益率が40%(利益は80万円)
こういった数字を把握していなければ、つい「売上の多いAを強化しよう」と判断してしまいがちですが、実は利益面ではBの方が会社に貢献しているのです。
このように、売上に目を奪われず、利益の構造を見抜く視点を持つことが、経営者にとっての最重要スキルです。
利益構造を把握するには、「部門別損益」や「商品別粗利」を作成するのが効果的です。エクセルでも十分です。まずは3つの主力商品について、売上・原価・利益を毎月記録してみてください。
5.3. 経営会議や銀行交渉で“数字を使って説明”する
数字を見る力、利益を分析する力が身についたら、いよいよ最後のステップ。それは、「数字を使って説明する習慣」です。
銀行との面談、社員との経営会議、税理士との打ち合わせ—こうした場面で、つい「感覚」や「感情」で話していませんか?
たとえば、「今年は業績が良くなってきている気がします」ではなく、「前年同月比で売上は12%増、営業利益は2.5倍になっています」と言えるようになる。
あるいは、「この新規事業は期待できそうです」ではなく、「初月は広告費20万円で売上が80万円、粗利率は35%でした。今後は広告効率を上げて、利益率を40%に高める計画です」と説明できるようになる。
経営者が“数字で語れる”だけで、説得力・信頼性・影響力が一気に高まります。
数字を使って説明することで、
・銀行との交渉がスムーズになる
・社員の納得感が高まる
・外部の専門家(税理士やコンサル)との連携が強くなる
こうした効果が連鎖的に生まれ、会社全体が前向きに、論理的に動き出します。
はじめはメモを見ながらでも構いません。まずは「数字を言葉にする」経験を重ねていくことが、最も確実な成長への道となります。
今すぐ始めよう。未来を数字で語れる経営者へ
“数字で語れる社長”になることは、難しいことではありません。必要なのは「毎月数字を見る」「利益構造に目を向ける」「数字で話す」—この3つの実践だけです。
これは、業種にも年齢にも関係ありません。どんな会社であっても、どんな経営者であっても、今この瞬間から始めることができます。
未来を語るなら、感覚ではなく、数字で語れる経営者になろう。
それが、銀行に信頼され、社員に期待され、会社が強くなる最も確実な一歩です。
まとめ
経営において「数字が苦手」はもはや通用しない時代です。銀行は決算書の表面だけでなく、その数字をどう理解し、どう活かそうとしているかを見ています。つまり、数字の意味を自ら語れるかどうかが、融資を引き出せるか否かの分かれ道となるのです。
数字に強い社長は、常に「資金繰り表」や「利益構造」を自分の言葉で説明し、経営の現状と未来を論理的に語ります。その姿勢が銀行に安心感を与え、結果として有利な条件での資金調達につながっています。
一方、数字で語れない社長は、「税理士に任せているから」「売上は伸びているから大丈夫」といった勘や思い込みに頼りがちです。これでは、銀行から見て返済の見通しが立たず、支援の対象から外れてしまう可能性があります。
数字で語れる経営者になることは、銀行との交渉力を高めるだけでなく、社員や取引先との信頼関係を強固にし、会社全体を成長へ導く武器となります。
そしてそれは、特別なスキルではありません。毎月の試算表を確認する、利益構造を可視化する、数字で未来を語る—この地道な積み重ねによって、誰でも身につけることができます。
今日から一歩踏み出して、「数字で語れる社長」としての道を進んでいきましょう。それこそが、次の融資、そして未来の飛躍を手にするための最短ルートです。
コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。

