社員が辞める本当の理由は“人事制度がないこと”だった!
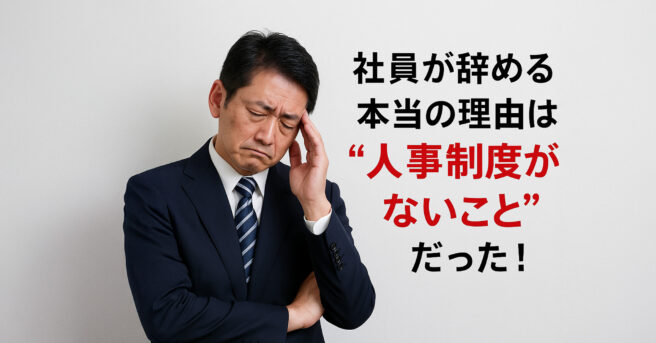
「最近、社員が次々と辞めていってしまって…原因がよくわからないんです。給料もそれなりに払っているし、職場の人間関係も悪くないと思っていたんですが…」
―これは、当社の個別相談に参加されたサービス業のオーナー社長からの声です。
確かに、社員の離職理由がはっきりしないまま、現場が回らなくなって困っているという経営者は少なくありません。
求人を出しても人が集まらない。やっと入社しても定着せず、数ヶ月で辞めてしまう。
「今の若者は根気がないのか?」「うちの魅力が足りないのか?」と悩む気持ちはよくわかります。
しかし、果たして問題は“社員側”だけにあるのでしょうか?
実は、社員が辞める本当の理由は「人事制度が存在しないこと」にある―
この事実に気づかずにいると、どれだけ採用をがんばっても、組織の根本は変わりません。
本コラムでは、社員が安心して働き、長く定着し、自ら成長していく組織をつくるために、なぜ中小企業にこそ人事制度が必要なのか、その理由と導入ステップをわかりやすく解説していきます。
はじめに
「制度なんて大企業の話でしょ」「社員数が少ないうちはいらない」
そう考えて、人事制度の導入を後回しにしていませんか?
実は、社員の離職が続く中小企業ほど、制度が整っていない傾向があります。
そして、多くの経営者が見落としているのが、制度がないこと自体が、社員の不満や不安を生み出しているという事実です。
給与や評価の基準があいまいなまま、社長の感覚だけで決められている。
仕事を頑張っても、どうすれば昇給・昇格できるのかが見えない。
そんな状況では、社員が「この会社で長く働こう」と思えるはずがありません。
人事制度とは、社員の「やる気」や「定着」を支える仕組みです。
評価・報酬・育成がバラバラでは、組織は機能しません。逆に、これらを一貫して設計することで、社員の納得感・成長意欲・信頼が高まり、組織に安定と成果が生まれます。
特に、今の若手社員は「感覚」では動きません。
自分がどう評価され、どこに向かって成長できるかを明確に求めています。
そこに答えられない会社は、いずれ人材の流出に直面します。
「制度」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、実際に中小企業に必要なのは、大企業のような複雑なシステムではありません。
自社の価値観に合ったシンプルな設計で十分なのです。
このコラムでは、なぜ制度がないと社員が辞めるのか、そして中小企業が最初に取り組むべき人事制度の考え方と導入のステップをお伝えします。
人が辞めない会社をつくるには、制度づくりから逃げないことが出発点です。
ぜひ最後までご覧ください。
1. 社員が辞める本当の理由は“制度不在”にある
中小企業の経営者から「最近、優秀な社員が続かない」「何が不満なのかわからないまま辞めていく」といった相談を受けることがあります。
業績もそこまで悪くないし、給与も周囲より低いわけではない。社長自身も社員を大切にしているつもり…。にもかかわらず、なぜ人が辞めてしまうのか。
それは、決して社員の「わがまま」や「忍耐力の欠如」ではありません。
制度が存在しない、あるいは機能していないことが、社員の離職の本質的な原因になっているのです。
制度とは、「評価・報酬・育成」などを明確に定め、誰がどう働き、どう成長していくかを可視化するための仕組みです。
制度がない状態は、例えるなら「地図も道しるべもない登山」を社員に強いているようなもの。
目指す山頂がわからず、進むルートも不明確。そんな状態では、途中で不安になり、立ち止まり、やがて離れていくのは当然です。
ここでは、制度がないことで起きる代表的な3つの問題を取り上げ、なぜそれが離職につながるのかを掘り下げていきます。
1.1. 給与や評価が「あいまい」なままでは社員は不安になる
ある中小企業の事例です。
社員は一生懸命働き、売上にも貢献していましたが、ある時こう言いました。
「自分が何を基準に評価されているのかがわかりません。頑張っても、頑張らなくても給料はあまり変わらないし…」
この声は、多くの中小企業に共通する悩みを物語っています。
評価基準が明確でないと、社員は“どう頑張れば報われるのか”が見えず、不安を抱えたまま働くことになります。
これは仕事への意欲を低下させるだけでなく、「報われない」と感じた時点で退職を検討する動機にもなります。
また、評価と報酬が連動していない場合、「給料は社長の気分次第」と感じる社員も少なくありません。
社長にとっては“感覚”でも、社員にとっては人生を左右する「生活の基盤」です。
報酬が恣意的だと受け取られた瞬間、組織への信頼は一気に崩れます。
給与や賞与の金額そのものが問題なのではありません。
納得感のある説明と、評価のルールが存在していることが重要なのです。
制度があることで、「これを達成すれば昇給できる」という指針が見え、社員は目標を持って働くことができるようになります。
1.2. 成長の道筋が見えないと“未来に期待できない”
もう一つ、よくある離職理由として、「この会社で成長していける気がしない」という声があります。
これも、制度が整っていないことに起因する問題です。
社員は、いま現在の仕事内容だけでなく、「この先、自分がどう成長できるのか」「どんなポジションを目指せるのか」を見ています。
将来像が見えないと、人は“今の仕事に意味があるのか?”と感じてしまうのです。
等級制度やキャリアパス制度は、まさにその「成長の地図」を描くためのものです。
たとえば、「入社3年でチーフを目指せる」「管理職になるためにはこういう経験が必要」といった道筋があるだけで、社員は自分の未来に期待が持てます。
逆に、「とりあえず今のまま頑張って」と言われ続けると、どれだけ努力しても“何が変わるのか”がわかりません。
やがて、モチベーションは低下し、「自分の未来は他の会社にあるかもしれない」と思い始めます。
制度がある会社では、社員が「今の努力は未来につながっている」と実感できます。
この感覚が、人材の定着と成長の最大の原動力になるのです。
1.3. 「不公平感」が社内に蔓延すると、空気が悪くなる
中小企業では、特定の社員が社長に可愛がられたり、昔からいる社員が優遇されたりといった、いわゆる“暗黙のルール”が残っているケースが少なくありません。
制度がない場合、このような“見えない差”が積み重なり、やがて不公平感という形で職場全体の空気を悪くしてしまいます。
社員は意外と周囲をよく見ています。
「あの人は遅刻しても許されるのに、自分は怒られる」
「なぜ彼だけ昇給したのか説明がない」
そんな声が広がれば、信頼もモチベーションも一気に下がります。
人は結果よりも「公平なプロセス」を重視します。
同じ評価基準のもと、同じルールで評価されていると実感できることが、安心して働ける組織文化を生み出します。
制度がなければ、評価はブラックボックスです。
「言った者勝ち」「社長に気に入られた者勝ち」になれば、真面目に働く社員ほど損をする構図が生まれます。
その結果、優秀な社員ほど早く辞めてしまうという本末転倒な事態に陥ってしまうのです。
制度がないことは、単に仕組みが足りないという問題ではありません。
それは、社員が安心して働き、未来を描き、努力を続ける「理由」を奪っているということです。
社員が辞める本当の理由は、“制度がないから仕方がなかった”という諦めの積み重ねなのです。
次章では、なぜ中小企業にこそ制度が必要なのか、そしてその導入がなぜ業績向上と直結するのかについて掘り下げていきます。
2. 人事制度がない中小企業で起こりがちな3つの誤解
中小企業の現場を訪問すると、人事制度について以下のような声を聞くことがあります。
「うちは社員数が10人しかいないから制度なんて不要でしょ」
「昔からいる社員とは家族みたいな関係だから、制度なんて堅苦しいだけ」
「評価?ちゃんと頑張っている社員は見てるから大丈夫」
これらの言葉に共通しているのは、制度がないことを“問題である”とは考えておらず、むしろ“わざわざ整える必要がない”という前提です。
しかし、こうした考え方は、結果的に会社の成長を止め、社員のやる気を削ぎ、離職率を高めてしまいます。
この章では、人事制度の導入を妨げている典型的な「3つの誤解」を取り上げ、それぞれがいかに組織に悪影響を与えているかを整理していきます。
2.1. 「人数が少ないから制度は不要」…は本当か?
最も多く聞くのがこの言葉です。「社員が数人しかいないから制度なんていらない」
一見、理にかなっているように思えるこの意見こそが、実は離職の原因を見逃す最大の要因になっています。
たしかに、大人数の会社と比べれば制度の複雑さは必要ありません。
しかし、制度の“有無”そのものは、組織規模に関係なく、社員の働く安心感に直結します。
人数が少ないからこそ、制度を整えることで「公平性」や「方向性」を明確にし、チーム全体が一枚岩になれるのです。
たとえば5人の会社でも、「この評価軸で昇給が決まる」「この行動が求められる」とルールが共有されていれば、社員同士の信頼関係が築きやすくなります。逆に、制度がなければ、その時々の社長の感覚で物事が決まることになり、社員の中に「納得できない」という感情が積もっていきます。
また、人数が少ないからこそ、一人の離職の影響が大きく、補充や再教育にかかるコストも甚大です。
小規模企業にとってこそ、人材の定着と育成は「事業存続」に直結する重要課題なのです。
2.2. 「ウチは家族的な会社だから」でごまかせる時代じゃない
もうひとつの誤解が、「ウチはアットホームな会社だから制度なんて必要ない」という考え方です。
この発想は、社員数が10〜30名程度の中小企業に多く見られます。たしかに、日常的に社長や役員と社員が顔を合わせる環境では、ある程度の“空気”で物事が回ることもあります。
しかし、時代は確実に変わっています。
「家族的経営」は、若手社員にとって“安心”ではなく“曖昧で不透明”なものとして映るのです。
たとえば、「お前のことはよくわかっているから、来月から少し給料上げるよ」といった評価の仕方。
年配社員には受け入れられても、若手社員には「何が評価されたのか、なぜ昇給したのか」が見えません。
また、「長くいる社員のほうが社長と仲がいいから優遇される」といった空気が蔓延すれば、新しく入った社員ほどやる気を失います。
“仲の良さ”と“仕事の成果”が混在している会社では、公平性が失われ、組織が分裂していきます。
現在は労働市場も変化し、多様な価値観を持つ人材が働く時代です。
「ウチの社風に馴染めないなら辞めてもらって構わない」という発想では、人材は定着しません。
人事制度は「人を縛るため」ではなく、「人が安心して働き、成長できるため」に必要な道しるべです。
「家族的経営だから制度はいらない」は、もはや通用しない時代に入っています。
2.3. 社長の“感覚評価”が組織のモチベーションを壊す
「普段から社員を見てるから、頑張ってる奴はちゃんと評価してるよ」
これは、感覚的評価を正当化する社長の典型的な言葉です。
もちろん、社長が現場に目を配り、努力を見逃さないのは素晴らしいことです。
しかし問題は、それが「誰にでも伝わる形で共有されていない」という点にあります。
評価というのは、結果や印象だけでなく、プロセス・姿勢・改善意欲など、様々な観点から見て初めて公平性を持ちます。
「なんとなく頑張ってる」「感じがいい」という評価では、他の社員が「じゃあ自分はどうすれば評価されるのか?」という疑問を持ち、やる気を失ってしまいます。
感覚評価がもたらす最大の問題は、“納得感のなさ”です。
同じ成果を出していても、発言力がある社員だけが評価される。
あるいは、社長の好みによって賞与やポジションが左右される。
これでは、努力しても報われないと感じる社員が増えてしまうのも無理はありません。
また、感覚で評価している社長は、自分の基準が社員にどう受け取られているかに無自覚なことが多く、「評価に不満があるなら辞めればいい」と開き直ってしまうケースもあります。
感覚評価は、知らず知らずのうちに社員の信頼を損なっていく最も大きな要因なのです。
評価制度は、社長の目線と社員の行動をつなぐ“翻訳装置”のような役割を果たします。
誰が見ても同じ基準で評価されているという「公平な仕組み」があることで、社員の行動にも一貫性と自発性が生まれます。
この章で紹介した3つの誤解は、どれも経営者が無意識のうちに陥りがちな“思い込み”です。
そして、その思い込みが、制度の整備を妨げ、優秀な人材の離脱を招いています。
「小さい会社だから制度はいらない」は、もはや通用しない時代です。
中小企業だからこそ、制度が「見える化」されていることで、社員が安心して成長できる環境が整い、ひとりひとりの力を最大限に活かせるようになります。
次章では、なぜ中小企業に制度が“向いている”のか、その理由と効果についてさらに深掘りしていきます。
3. なぜ中小企業にこそ人事制度が必要なのか?
多くの中小企業では、人事制度の整備が後回しにされがちです。
「制度を整えるより、まずは売上を上げたい」
「今は人も少ないし、制度を作るタイミングではない」
このような考えが現場には根強くあります。
しかし、その考え方こそが、離職率の上昇、生産性の低下、組織の成長鈍化を招いている大きな要因になっているのです。
制度というと「堅苦しい」「コストがかかる」というイメージを持たれがちですが、実際には制度を整えることで、社員が安心し、自発的に動き、結果として業績が上がるという好循環が生まれます。
ここでは、なぜ中小企業こそ人事制度を整備すべきなのかを、3つの視点から解説します。
3.1. 明確な基準が「安心感」と「納得感」を生む
まず、制度が整っていない状態では、社員は常に「不安」を抱えながら働くことになります。
「自分の働き方は正しいのか?」「どれだけ成果を出せば評価されるのか?」といった疑問が、日々の業務の中で解消されないまま積み重なっていきます。
特に中小企業では、社長と社員の距離が近く、評価や報酬の判断が「社長の一言」で決まることも少なくありません。
それが上手く機能しているうちは問題ないように見えますが、社員が増えたり、組織が広がったりすると、“あいまいさ”が不満や不信感に変わり、組織全体の士気を下げてしまうことになります。
逆に、制度によって「この成果を出せば昇給」「この行動が評価対象」といった明確な基準が示されることで、社員は納得感を持って仕事に取り組むことができます。
同時に、「自分はちゃんと評価されている」という安心感が働きやすい環境をつくり出します。
この納得感と安心感があるからこそ、社員は「会社に貢献しよう」「ここで成長しよう」と思えるのです。
3.2. 「育成」と「定着」の仕組みが業績に直結する
中小企業にとって、人材の育成と定着は命綱とも言えるテーマです。
一人の社員が担う業務の幅が広く、育った人材がそのまま“戦力”となるため、採用以上に“育てる”ことが重要になります。
ところが、制度がない会社では、育成が「現場任せ」「感覚任せ」になりがちです。
「経験して覚えてもらう」「見て学んでもらう」といった属人的な育成では、個人差が生まれ、育つスピードも安定しません。
結果として、育成に時間がかかりすぎたり、「育たないから辞めさせる」といった悪循環に陥ってしまいます。
制度を整えることで、育成のステップを明確にし、誰でも一定レベルまで育つ仕組みを構築することが可能になります。
たとえば、「入社3ヶ月でこれを覚える」「半年後にはこれができるようになる」といった基準があることで、本人も上司も進捗を共有でき、指導の質も高まります。
さらに、明確な評価と報酬の基準があれば、社員が「努力すれば報われる」と実感できるようになります。
これが離職の抑制につながり、安定的に人材が定着する組織づくりの基盤となります。
業績とは、仕組みによって成長する人材が、現場でパフォーマンスを発揮し続けることで初めて実現するものです。
中小企業の業績は、人材力に直結しているからこそ、制度による「育成」と「定着」の仕組みが欠かせないのです。
3.3. “制度がある会社”が若手人材に選ばれる時代
近年、新卒採用や若手人材の中途採用において、「人事制度があるかどうか」を重視する傾向が高まっています。
特にZ世代と呼ばれる若い世代は、「評価の透明性」や「働き方のルール」「成長環境の有無」といった点を重視し、企業選びをしています。
つまり、制度が整っていない中小企業は、若手人材にとって“選ばれにくい会社”になってしまうということです。
これは能力や待遇の問題ではありません。
どれだけ魅力的な事業内容であっても、「この会社でどう評価され、どう成長できるか」が見えなければ、安心して入社することができないというのが、今の若手の本音なのです。
また、採用面接の際に「評価制度はどうなっていますか?」「キャリアパスは用意されていますか?」と聞かれることも珍しくなくなっています。
そのときに明確な説明ができなければ、他社に流れてしまうのは時間の問題です。
制度があることは、単に“社内向けの仕組み”にとどまりません。
会社の信頼性や将来性を示す「外部への発信力」そのものでもあるのです。
中小企業が優秀な若手人材を確保し、組織を次の成長フェーズへと導いていくには、「制度があること」が必須条件になりつつあることを認識すべきです。
中小企業の多くは、「今ある人材でどう成果を出すか」を常に模索しています。
その中で、人事制度というのは決して“贅沢なオプション”ではありません。
むしろ、「人材が安心して働き、成長し、成果を上げ続ける組織をつくる」ために、最も効果的な仕組みです。
明確な基準は社員の安心感と納得感を生み、育成と定着のサイクルが業績を押し上げ、制度の有無が人材採用力を左右する時代。
まさに今こそ、中小企業が制度を整えるべきタイミングです。
次章では、実際に制度導入を進める際に、中小企業が最初に取り組むべき“シンプルな制度設計”についてご紹介します。
4. 制度づくりは「シンプル」でいい。
「制度は必要だとわかっている。でも、うちには難しそうだ…」
多くの中小企業の経営者がこのように感じています。
実際、大企業のように分厚い人事制度マニュアルを見せられたら、腰が引けてしまうのも無理はありません。
しかし安心してください。
中小企業に必要な制度は、複雑なものである必要はありません。むしろ“シンプルな設計”こそが、うまく機能するポイントです。
制度の導入で大切なのは、「最初から完璧を目指さないこと」。
まずは小さく始めて、徐々に育てていけばよいのです。
ここでは、今すぐにでも取り組める実践的な制度構築のステップを3つの柱に分けてお伝えします。
4.1. はじめは「等級制度+評価制度+賃金制度」の3本柱で十分
中小企業の制度設計において、最初に整備すべきは次の3つです。
・等級制度(役割やレベルの分類)
・評価制度(行動や成果をどう見るか)
・賃金制度(給与や賞与の決め方)
この3本柱が整うだけで、組織内の「見えない不公平」や「基準のあいまいさ」が大幅に解消されます。
とくに等級制度は、社員の「位置づけ」と「成長段階」を明確に示す軸として重要です。
「新人 → 一人前 → リーダー → 管理職」など、自社の業務や人数に合わせて段階を設定するだけでも、社員は自分の立ち位置を把握しやすくなります。
次に評価制度ですが、「成果」だけでなく「行動」や「姿勢」を評価項目に加えることがポイントです。
成果主義に偏りすぎると、チームワークや継続的な努力が軽視され、組織文化が壊れてしまう可能性があります。
そのため、「お客様対応の姿勢」や「チーム内での協力姿勢」なども項目に取り入れると、社員全体の動きが良くなります。
最後の賃金制度は、評価と連動させることが最大のポイントです。
「評価が良ければ昇給・賞与に反映される」仕組みがあるだけで、社員は目標に向かって努力しやすくなります。
この3つの制度が最低限整えば、社員にとっても「どうすれば認められるか」「どう成長できるか」が見えるようになります。
4.2. 自社の価値観に合った制度設計が社員の共感を生む
制度を設計する際に、外部のフォーマットや他社事例ばかりを真似しようとすると、うまくいかないことがあります。
なぜなら、制度は“会社の価値観”と“社員の現実”に合っていなければ、定着せずに形骸化してしまうからです。
たとえば、「利益だけを追う営業姿勢より、お客様との信頼関係を重視する」という方針がある会社であれば、その価値観に基づいて「お客様との信頼構築」を評価項目に入れるべきです。
あるいは、「チャレンジ精神を応援する文化」を大切にしているのであれば、「新しい提案をした回数」や「改善アイデアの提出」などを行動評価に盛り込むことが自然です。
制度とは、社長の想いと社員の行動をつなぐ“翻訳機”のようなものです。
どんな会社を目指しているのか、どんな行動を大切にしたいのかを、制度として社員に“見える形”で伝えることが、共感と自発性を生み出すのです。
テンプレート通りに制度を設計するのではなく、会社ごとにカスタマイズすることで、社員から「これはうちの会社らしい」と納得され、制度が機能するようになります。
4.3. 「運用の仕組み」こそ制度の生命線になる
せっかく制度を設計しても、「導入して終わり」では意味がありません。
制度というのは、動かし続けて初めて意味があるものです。
多くの中小企業がつまずくポイントが、まさに「運用がされない」「途中で止まってしまう」という問題です。
たとえば、評価制度をつくったが、評価シートの記入がされない。
評価はしているが、面談がなく、社員にフィードバックが届かない。
昇給のルールを作ったものの、「今回は特例で…」といった例外を繰り返す。
こうなると、社員はすぐに「どうせ制度なんて意味がない」と感じ、制度は形骸化します。
制度は設計よりも「継続的に運用できる仕組みづくり」こそが最大の勝負所なのです。
そのためには、以下のような工夫が有効です。
・年2回の評価面談を必ず実施するルールを設ける
・面談内容はフォーマット化して記録に残す
・昇給・賞与決定のプロセスを社内で共有する
・毎年1回、制度内容の見直しと社員アンケートを実施する
こうした小さな仕組みを地道に積み上げていくことで、制度はようやく「社員にとって信頼できる仕組み」となっていきます。
制度はつくることが目的ではなく、社員が安心して働き、会社とともに成長していくために“生かす”ことが本当の目的です。
制度設計は、専門家に任せなければできないものではありません。
そして、決して難解なフレームワークを導入する必要もありません。
自社の実情に合った、シンプルで運用可能な制度づくりこそが、中小企業にとって最も成果の出るスタートラインです。
次章では、制度を「絵に描いた餅」に終わらせないために、社長自身がどう関わっていくべきかを解説していきます。中小企業の組織力を高めるうえで最も重要な視点です。
5. 社長が主導する制度改革こそ、最強の組織改革
制度をつくること自体は、ある意味で簡単です。
専門家に頼めば形は整いますし、マニュアルやテンプレートも世の中に数多く存在します。
しかし、現実には制度を「つくっただけ」で終わってしまう中小企業が圧倒的に多いのです。
では、なぜうまくいかないのでしょうか。
答えはシンプルです。
社長が制度の本質を理解せず、“運用の主導者”になっていないからです。
中小企業における制度改革とは、単なるルールづくりではありません。
それは、組織文化そのものを変える「経営のアップデート」です。
そして、その変化を最も加速させるのは、制度の旗振り役としての社長自身なのです。
この章では、社長がどのように制度改革に関わることで組織が変わるのか、3つの視点からご紹介します。
5.1. 制度は“導入”より“浸透”が勝負
人事制度をつくったものの、実際には「誰も中身を知らない」「評価が形骸化している」「面談もやっていない」といった声はよく聞きます。
制度改革の失敗は、ほとんどがこの“運用段階”にあります。
特に中小企業では、人事部門が存在しない、または一人しかいないというケースが多く、社長自身が主導して制度を“現場に根づかせる”動きがなければ、制度は絵に描いた餅のまま終わります。
制度が機能するかどうかの分かれ道は、「導入できたか」ではなく、社員が“自分ごと”として制度を理解し、日々の行動に結びつけているかどうかです。
そのためには、社長が率先して次のような行動をとることが不可欠です。
・評価面談の場に社長も参加する
・日常の中で制度の内容に触れる
・全社員の前で「この制度を大切にする」と明言する
このように、社長自身が制度の存在を常に意識し、行動で示すことで、社員も「これは会社として本気なんだ」と感じ、制度に対する信頼が育まれていきます。
5.2. 「理念×制度」が、会社の文化をつくる
制度は単なるルールやフォーマットではなく、会社の“価値観”を具現化した仕組みです。
制度の根底に理念がないまま運用すると、制度は社員にとって“義務”にしかなりません。
逆に、制度と理念が結びついているとき、社員は「なぜこの制度が存在するのか」「何を大切にして働くのか」を自然と理解するようになります。
たとえば、「チームワークを重んじる会社」が「個人業績だけを評価する制度」を導入したらどうなるでしょうか?
制度と文化が矛盾し、組織の空気はバラバラになります。
逆に、「顧客満足を大切にする会社」が「お客様評価」や「クレーム改善提案」を評価項目に組み込んでいたら、社員はその理念を“自分の行動指針”として受け止めやすくなります。
つまり、制度は経営理念の“実践の道具”なのです。
理念があり、それを社員の行動に落とし込む手段として制度がある。
この2つが連動することで、「理念に沿った文化」が組織に根づいていくのです。
中小企業こそ、この「理念×制度」の一貫性を大切にすることで、組織に強い軸が生まれます。
5.3. 社長が“制度の番人”になることで社員の信頼が高まる
制度を運用していく中で、必ず現れるのが「例外」です。
「今回は事情があるから評価を特別に」「長年頑張ってきた社員だから昇格させたい」
その気持ち自体は悪いものではありません。
しかし、こうした“特別対応”を繰り返すと、制度は一気に信頼を失います。
そこで必要なのが、社長が「制度の番人」として、ルールを守り抜く覚悟を示すことです。
社員は常に「公平性」を見ています。
「誰かがルールを破ったのに、見過ごされている」
「頑張っても評価されず、気に入られている人が優遇される」
そうした事態が起きれば、真面目な社員ほどモチベーションを失い、いずれ離れていきます。
制度とは、社長自身が率先して守り、説明責任を果たすことで、初めて社員にとって「信頼できる仕組み」になります。
制度を作ったら、社長自身が最も厳しく制度を守る。
不満の声が出たときこそ、「それがうちのルールです」と毅然と説明する。
特例を求められたら、「制度に従って判断します」と言い切る。
この姿勢が、社員の目に“信頼できるリーダー”として映り、制度の定着と組織力の向上につながっていきます。
中小企業にとって、制度改革は「仕組みを整える」だけでなく、「組織文化をつくり直す」行為でもあります。
それを実現する最大の原動力は、制度づくりに本気で向き合う社長の姿勢そのものです。
制度を生かすも殺すも、社長次第。だからこそ、社長が本気で関わることで、制度は“組織を変える力”へと進化します。
制度改革は一度整えて終わりではなく、浸透し、文化となり、世代を超えて機能し続けていくものです。
その起点に立つのが、社長という存在であることを、ぜひ忘れないでください。
次は、制度導入によって実際に成果が出た中小企業の事例をご紹介し、制度が組織と業績にどう影響するのかを具体的に解説していきます。
まとめ
社員が辞めてしまう理由は、給与や待遇だけではありません。
むしろ多くの場合は、「どう評価されているのかわからない」「この会社で成長できる未来が見えない」という“見えない不安”が積み重なった結果なのです。
中小企業では、「人数が少ないから」「アットホームだから」といった理由で制度づくりを後回しにする傾向があります。
しかし、そうした会社ほど、社員の不満がくすぶり、せっかく育った人材が離れていくリスクが高まります。
だからこそ、まず取り組むべきは、等級・評価・賃金の3本柱を中心にした“シンプルな制度設計”です。
それだけでも、社員にとっては「何を目指せばよいのか」「頑張りが報われる仕組みがあるのか」が見えるようになります。
さらに大切なのは、それを制度として“動かす”こと。
どんなに立派な制度でも、現場に浸透しなければ意味がありません。
制度改革の主導者は、間違いなく社長です。
社長が制度の意義を語り、自らも運用に関わり、例外をつくらず守り抜く姿勢を示すことで、社員は「本気なんだ」と信じるようになります。
制度は、人を縛るものではありません。
社員が安心して働き、自分の未来に期待し、組織とともに成長するための“道筋”なのです。
中小企業にとって、最大の競争力は「人」です。
その人が辞めず、育ち、力を発揮し続ける環境を整える――
それこそが、人事制度をつくる本当の意味であり、企業の未来を支える土台となります。
コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。

